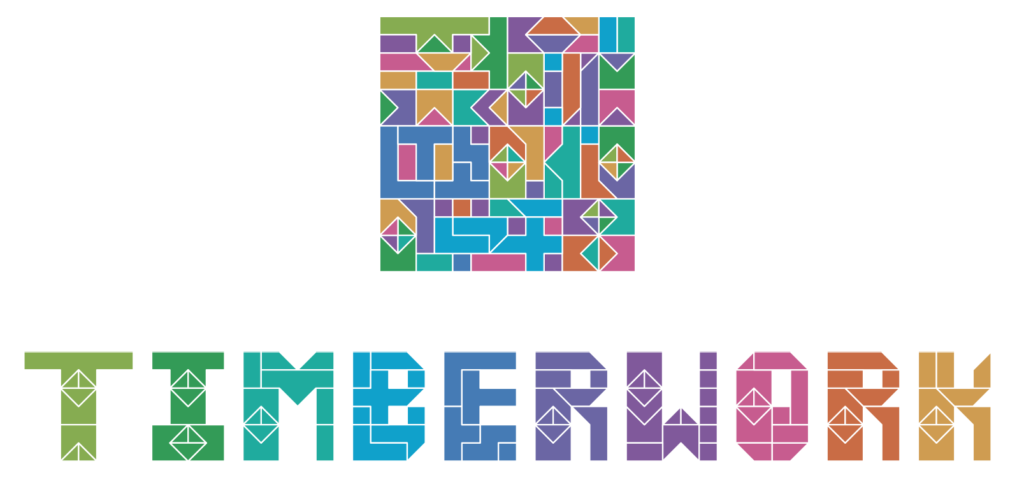2022年 夏の間の活動報告!
こんにちは!! 春の活動報告から、ブログはご無沙汰しておりましたが、みなさんお元気でした…
春の活動報告~その参~
春の植樹イベントの様子をお伝えする活動レポート第3弾! 第1弾・第2弾では毎週のように行…
春の活動報告~その壱~
みなさん、こんにちは! 数年ぶりに行動制限のないゴールデンウィーク。観光地ではコロナ前ほ…
「第一回湯守の森会議 里山循環社会を目指して〜鳴子湯守の森」・後編
東鳴子の大沼旅館山荘でシンポジウム・馬搬実演が開催されました。 3月15日は、馬搬の実演…
第一回湯守の森会議 里山循環社会を目指して〜鳴子湯守の森
東鳴子の大沼旅館山荘でシンポジウム・馬搬実演が開催されました。 3月13日〜3月15日に…
エコラの森にて植林活動を行いました
2014年5月24日に恊働団体のNPO法人日本の森…
里山資本主義 〜地元を活かす豊かな暮らし(システム)
公益財団法人みやぎ環境とくらしネットワーク開催のイベントにブース出展しました。 2014…